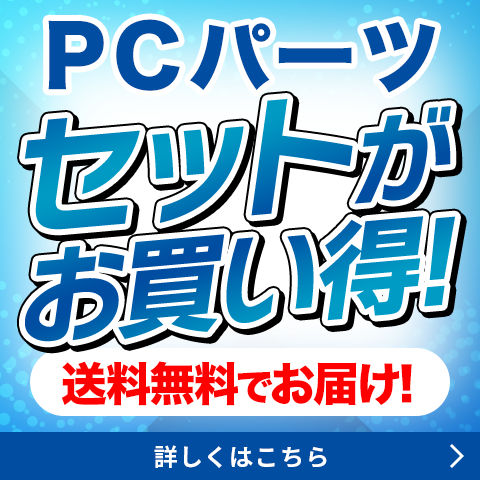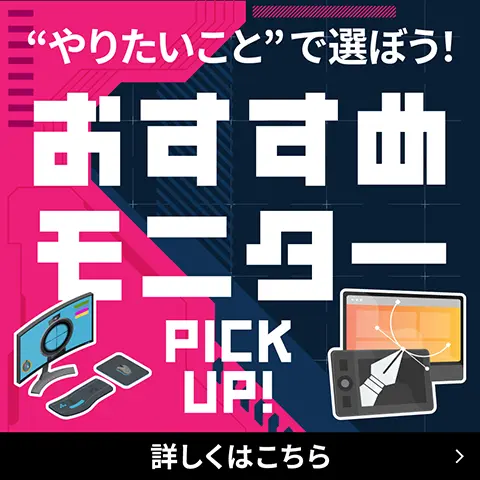マイク(パソコン用)
マイクとは?
パソコンと接続し、リモート会議や動画配信、ボイスチャットなどでマイク機能を使えるようにするデバイスです。
イヤホン・ヘッドセットのマイクよりも音質やノイズカットを重視しやすいため、通話環境を整えるのに欠かせません。
マイクの選び方ガイド
選び方のポイント
パソコン用のマイクは、形状や接続方法が様々あります。
どのように選ぶべきか、用途ごとの選び方や指向性の違いもまとめました。
-
1.マイクの形状の選び方
パソコン用のマイクは、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの2種類が主流です。
通話用にはダイナミックマイクが一般的ですが、動画配信では繊細な音を拾えるコンデンサーマイクも人気があります。ダイナミックマイク
 カラオケやライブ等のボーカルで使用される。
カラオケやライブ等のボーカルで使用される。
周囲のノイズを拾いにくく、大きな音の入力も可能。
電源不要で使用できる。コンデンサーマイク 楽器の演奏などレコーディングで使用される。
楽器の演奏などレコーディングで使用される。
繊細な音を拾いやすく、近年動画配信でも人気。
電源接続が必要。 -
2.マイクの接続方法の違い
パソコン用のマイクは、同じ有線接続でも端子によって遅延や音質に違いがあります。
一般的にはUSBマイクが広く利用されていますが、配信など音質を重視する場合、プロ向け仕様のマイクが選ばれることもあります。ミニプラグ
 パソコンやスマートフォンなどで一般的。マイクは4極のミニプラグが主流。
パソコンやスマートフォンなどで一般的。マイクは4極のミニプラグが主流。
2極、3極の端子では使用できないため注意。USB デジタル接続でパソコンに直挿しで使いやすい。ミュート・音量ダイヤル付きモデルも豊富。
デジタル接続でパソコンに直挿しで使いやすい。ミュート・音量ダイヤル付きモデルも豊富。
オーディオインターフェース不要で使用できる。フォーン スタジオ機器で定番の太いプラグ。ミキサーやオーディオインターフェースで使用される。
スタジオ機器で定番の太いプラグ。ミキサーやオーディオインターフェースで使用される。
変換ケーブルやインターフェース経由で使うことが多い。XLR プロ用のロック機構付きの端子。コンデンサーマイクの場合+48Vファンタム電源が必要。
プロ用のロック機構付きの端子。コンデンサーマイクの場合+48Vファンタム電源が必要。
ノイズに強く、安定性も高い。 -
3.用途に合わせた指向性も確認
指向性とは、マイクが音を拾う方向のことです。
例えば、単一指向性であれば一方の音だけを拾い、双指向性であれば、インタビューのように対面の音を拾います。
最適な指向性を選べばノイズを抑えられますが、用途に合わない指向性を持ったマイクの場合、ほしい音が収録できないこともあります。無指向性
 全方向をほぼ均等に収音する。
全方向をほぼ均等に収音する。
室内の残響も拾い、音の近い・遠いはない。
会議やピンマイク等で使用される。単一指向性 前方重視で、後方のノイズをカットする。
前方重視で、後方のノイズをカットする。
音の近い・遠いがわかりやすい。
配信や歌撮りなどでも使用される。双指向性 前後の音を拾い、左右のノイズをカットする。
前後の音を拾い、左右のノイズをカットする。
音の近い・遠いが最も分かりやすい。
対面インタビューやステレオ収録に使用される。
よくあるご質問・用語解説
マイク選びでよくあるご質問をまとめました。
頻出する専門用語やヘッドセットとの違いなど、マイク選びに役立つ情報が満載です。
-
Q1ヘッドセットと単体マイク、どちらを選ぶべきですか?
会議やボイスチャット中心ならヘッドセット、配信や録音、複数人で利用するなら単体マイクがおすすめです。
ヘッドセットは口元との距離が一定なため、自然な会話を楽しめます。場所を取らずお手軽に使えます。
単体マイクは設置位置の調整ができるため、動画の収録や複数人での利用に最適です。音作りやデスク環境を快適にしたい方に向いています。 -
Q2ノイズリダクションとはなんですか?
マイクに入る空調の音やキーボード音、環境ノイズを自動で抑える処理のことを言います。
ノイズキャンセリングが聴こえる音を抑える機能で、ノイズリダクションはマイクが拾う音を抑える機能です。
パソコンの通話アプリなどソフトウェア上で有効にでき、商品によってはマイクの機能として搭載しているものもあります。
強く効かせすぎると、声が小さくなったり途切れたりすることもあるため、小~中ぐらいで少しずつ調整しましょう。 -
Q3マイクスタンドやマイクアームは必要ですか?
ノイズが気になる方、デスクの広さを保ちたい方は用意するのがおすすめです。
ただ、マイクスタンドを使用してデスクに直接置くと、キーボードのタイプ音を拾ってノイズが発生することがあります。
ノイズを極力抑えたい方は、マイクアームを利用し口元や手元との距離を一定に保つよう設置しましょう。
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。